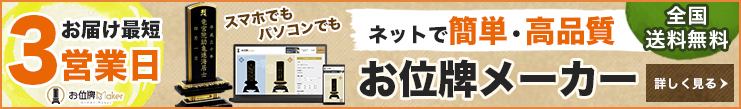位牌には戒名を入れるのが一般的ですが、本当に必要なものなのでしょうか。
この記事では、位牌に戒名を入れる理由や必要性について詳しく解説しています。
戒名の書き方や値段、戒名を構成する4つの要素についても解説しているので、位牌に戒名を入れたいと考えている方は参考にしてください。
位牌に入れる戒名とは
位牌にはなぜ戒名を入れるのでしょうか。
戒名の意味と必要性について解説します。
戒名の意味
「戒名(かいみょう)」とは、仏様の世界における故人の新しい名前のことです。浄土真宗では「法名(ほうみょう)」と呼ばれます。
仏教の教えに従い、極楽浄土を目指して修行する、仏弟子(ぶつでし)になったことを証明する名前です。
本来は出家した仏弟子が生前に与えられる名前ですが、出家していない方も亡くなった際に菩提寺の住職から授けてもらうことが一般的になりました。
また、仏教式の葬儀では位牌や卒塔婆に俗名(生前の名前)ではなく、戒名を記載します。
戒名の必要性
仏教では、俗名のままでは「仏の世界に向かえない」「極楽浄土にたどり着けない」といった考えがあります。
また、菩提寺がある場合は、戒名を授けられないとお墓に入れないというルールがあるのも事実です。
仏教式で葬儀を行う場合や、先祖代々の墓がある場合は、戒名が必要といえるでしょう。
戒名を授けられないことで菩提寺との関係が悪化してしまえば、子孫に迷惑がかかる可能性があります。
戒名を構成する4つの号
戒名には、次の4つの号が含まれています。
● 院号・院殿号
● 道号
● 戒名
● 位号
戒名を構成する号の意味や付け方について、詳しくチェックしていきましょう。
院号・院殿号
院号は、社会的に貢献度が高い方や信仰心の強い方に授けられます。
もともとは天皇や皇族、将軍家の戒名として使用されてきました。
戒名の一番上に、「~院」とつくのが特徴です。
院殿号は、院号に次いで位の高い方に付けられます。
院号と同様に戒名の最初に「~院殿」と付くのが特徴です。
院号と院殿号は、誰にでも付くわけではないため、使用されているケースは少ないといえるでしょう。
道号
道号は、仏道の修行により悟りを開いた者に授けられる称号です。
現代では、僧侶が故人の人柄や職業、居住地などを加味しながら、戒名とのバランスを考慮した上で決めるのが一般的です。
2文字の漢字で構成されるのが基本で、場所を表す文字や性格を表す文字、住居を表す文字がよく使用されています。
院号と院殿号がない場合は、道号が戒名の始まりです。
なお、道号は水子や幼児、未成年の方に付けることはありません。
戒名
戒名は故人の俗名に関連する文字や、経典からふさわしい文字を選出して付けられます。
仏の世界は平等であるという教えに従い、どのような身分の方でも戒名は2文字です。
先祖代々受け継いできた文字や、尊敬する方に通じる文字を使用することもできます。
ただし、天皇や著名人を連想させる文字、縁起が悪い文字、響きが悪い文字は使うべきではありません。
位号
位号は、戒名の最後に付ける、俗名でいえば様に当たる部分です。
社会的貢献度や信仰心の強さ、年齢や性別によって決められます。
男女別の位号のランクについては、成人男性と成人女性で上から高い順で表にまとめましたのでご確認ください。
成人男性 成人女性
大居士 清大姉
居士 大姉
大禅定門 大禅定尼
禅定門 禅定尼
清信士 清信女
信士 信女
水子や幼児、未成年の場合も、性別や年齢によって位号が異なります。
宗派によって異なる戒名の書き方

位牌に記す戒名の書き方は、宗派によって見分けることが可能です。
ここでは、位牌に入れる文字の位置や書き方を宗派別で解説します。
真宗・浄土真宗
真宗・浄土真宗の場合、戒名ではなく法名(ほうみょう)が授与されます。
阿弥陀如来からいただく名前のことを意味していて、ほかの宗派のように戒という言葉を使うことはありません。
浄土真宗では法名(戒名)の上に「釋」、もしくは「釈」を置きます。釋は釈の旧字です。
法名は位号を用いず、釋と2文字の法名のみで構成されます。
真言宗
真言宗の戒名には、一番上に「ア」の梵字が付けられます。
これは大日如来を意味しており、故人が大日如来の弟子になったことを示します。
なお、幼児の場合は地蔵菩薩を意味する「カ」の梵字が付けられます。
浄土宗
浄土宗は院号の後に道号を付けず、五重相伝を受けた方のみに授与される誉号を付けるのが特徴です。
また、位号には「禅定門」や「禅定尼」が用いられるケースがあります。
天台宗
天台宗は、基本的な院号、道号、戒名、位号の構成で戒名が作られることが多いです。
戒名の最初に、阿弥陀如来を意味するキリークの梵字や、大日如来を意味するアの梵字が付けられることもあります。
禅宗
禅宗も、基本的な構成は院号、道号、戒名、位号の順です。
ただし白木位牌の場合は、現世での務めを終えたのち仏の世界に帰る「新帰元」と記されることもあります。
日蓮宗
日蓮宗では、戒名ではなく法号が授けられます。
法号の場合は、戒名に当たる部分に「日号」を置くのが特徴です。
日号は、日と実名を合わせた文字にすることが基本になります。
戒名を作る場合の値段
戒名を作成するときや、位牌に入れるときには費用がかかりますが、どれくらいの値段なのでしょうか。
戒名の作成費用と、位牌に戒名を入れる費用の目安について解説します。
戒名を作成する費用の目安
戒名料の相場は、宗派や位号のランクによって値段が異なるため20万~100万円と幅があります。
位号のランクごとの相場の目安は、次のとおりです。
● 院居士・院大姉:100万円以上
● 院信士・院信女:80万~100万円以上
● 居士・大姉:50万~80万円以上
● 信士・信女:20万~50万円以上
戒名料はお布施として授与されたお寺に納めるため、料金設定が明確ではありません。
納めた戒名料が多すぎたり、少なすぎたりすることを避けるために、おおよその相場を把握しておきましょう。
位牌に戒名を入れる費用の目安
位牌に戒名を入れるための費用の相場は、1名あたり3,000円~10,000円です。
夫婦位牌で2名分入れる場合は、料金が倍になります。
戒名入れ代には、以下の文字加工代も含まれているので、覚えておきましょう。
● 梵字
● 戒名
● 没年月日
● 俗名
● 没年齢
これら5つの基本要素以外に文字を入れる場合は、追加料金が発生します。
なお、戒名を入れてもらう位牌は自分で購入するのが一般的です。
位牌の費用は、種類や加工方法によって異なりますが、10,000円~30,000円で購入できます。
位牌に入れる文字は、書くか彫るかを選択することも可能です。
位牌に戒名を入れるときのポイント

位牌への戒名入れは、石材店や仏具店に依頼するのが一般的です。
戒名入れを業者に依頼するときのポイントについて解説します。
ご先祖様の位牌がある場合は持参する
位牌に戒名入れを依頼する場合は、ご先祖様の位牌を持参してください。
なぜなら、位牌の文字は宗派やお寺によって細かく決められているため、口頭やメモで伝えると間違いが発生する可能性があるからです。
位牌を持ち運ぶときは、落としたりぶつけたりして破損しないように、風呂敷で包んで保護しましょう。
位牌が遠方にあるなど、事情があって持ち込めない場合は、位牌の裏と表の写真を持参しても問題ないです。
日にちに余裕を持たせる
位牌に戒名入れが完了するまでは、平均で2週間程度かかります。
お盆や年末年始などの時期は依頼が増えるため、2週間以上かかってしまうケースも多いです。
日程に余裕がないと、四十九日法要に間に合わない可能性があるので気を付けましょう。
文字色とレイアウトを決めておく
位牌の文字色やレイアウトは自分で決める必要があるため、事前に決めておくと依頼がスムーズです。
すでにご先祖様の位牌がある場合は考える必要がありませんが、初めての場合は手間がかかります。
文字色は、裏表どちらも金色にするケースが多いです。
ただし地域によって素掘りや黒色、青色、朱色の場合もあるので、お寺に問い合わせておくと安心できるでしょう。
戒名のレイアウトにルールはありませんが、表面の中央に戒名を、裏面の中央に俗名を記すのが標準のレイアウトになります。
しかし、ご先祖様の位牌がある場合は、その位牌に合わせてレイアウトするとよいでしょう。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をお客様のご要望に沿い、オーダーメイドで作成いたします。
さらに全国対応しており送料無料で、最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌をぜひ、お位牌Makerにご依頼してみてはいかがでしょうか。
戒名に関するよくある質問
最後に、戒名に関するよくある質問を3つご紹介します。
菩提寺がない場合は?
お世話になっているお寺がない場合は、自分で戒名を付けることもできます。
菩提寺がある場合は、住職との関係が悪化してしまうため、自分で付けることは控えましょう。
お寺の檀家にならなくても、戒名を授けてもらうことができるサービスもあります。
費用もリーズナブルで、葬儀後にお寺との付き合いを続けていく予定がない方におすすめです。
位牌に戒名を入れないのはあり?
信仰している宗教がない場合は、戒名なしでも問題はありません。
最近では、位牌に戒名を入れず、俗名のみで作る方も増えています。
俗名で位牌を作成する場合は、最後に「之霊位(のれいい)」を付けることで、戒名を入れた場合と同じ意味になることを覚えておきましょう。
夫婦位牌に戒名を入れる場合は?
位牌を一つにまとめる夫婦位牌では、戒名も連名で記載します。
あの世でも夫婦で一緒にいたいという考えよりも、残された家族の負担を考えて夫婦位牌を希望するケースが多いです。
2人分の戒名を入れる必要があるため、位牌のサイズは大きめのものを選択してください。
まとめ
今回は、位牌に入れる戒名について詳しく解説しました。
戒名は、あの世に旅立った故人の新しい名前です。
仏教を信仰しているならば、仏弟子になったことを証明するために、菩提寺の住職から授けてもらう必要があるといえます。
戒名は4つの号から成り立っていますが、宗派によって書き方に違いがあるので注意してください。
戒名料には明確な決まりがないため、お布施を納めるときにトラブルにならないように、費用の相場を把握しておきましょう。