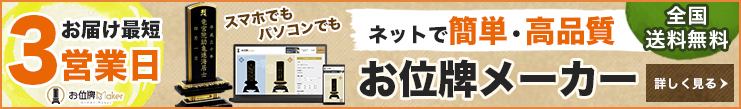位牌が必要となったとき、どのような位牌を作れば良いのか、参考としてインターネットで調べる方は多いのではないでしょうか。
しかし、位牌にはさまざまなタイプがあり、選び方が分からずに悩む方もいるはずです。
そこで本記事では、失敗しない位牌の選び方を詳しく解説します。
これから位牌を作る方は、ぜひ最後までご覧いただき、位牌選びの参考にしてみてください。
位牌を選ぶ基準
まずは、位牌を選ぶに当たり、どのような基準があるのか、詳しくご紹介していきます。
また、本当に位牌が必要かどうか、位牌の基本もお伝えするので、購入前に疑問を解消しましょう。
位牌の種類
位牌には大きく分けると2つの種類があり、それぞれで使用する目的が異なります。
葬儀から四十九日までに使用する「白木位牌」と、四十九日以降に「本位牌」です。
白木位牌は、一時的に使用するものであり「仮位牌」と呼ばれることもあります。
一方、本位牌はさまざまな素材や製法で作られており、ここでも種類を選ぶ必要があります。
そのため、使う時期に合わせて適切な位牌を選び、本位牌では好みや調和を考慮して種類を決めましょう。
サイズ
位牌にはさまざまなサイズがありますが、基本的に仏壇のサイズに合うものを選びます。
すでに仏壇へ先祖の位牌がある場合は、同じサイズか小さめのものを選ぶとよいでしょう。
また、戒名の文字数とのバランスも重要です。
戒名の文字数が多い場合は、きれいに収まる長さが必要となるため、特に注意してください。
デザイン
現在、位牌には漆や木目の伝統的なものから、モダンでおしゃれなものまで、さまざまなデザインがそろっています。
宗派によるデザインの制限がなく、自由に選べるため、仏壇や部屋のインテリアに合わせて選んでください。
また、故人様の好みに合わせて、イメージに合ったデザインを選ぶのもおすすめです。
そもそも位牌は必要?
結論から述べると、位牌は必ずしも用意すべきものとは限りません。
近年では、住宅事情や生活スタイルの変化により、仏壇を置かないご家庭も増えています。
その点、位牌は必ずしも仏壇に置くものではないため、仏壇がなくとも位牌があれば供養が可能です。
ただし、位牌があることにより、故人様を身近に感じられます。
部屋のインテリアになじむシンプルなものや、おしゃれなデザインのものなど、お好みの位牌を検討してみてください。
複数の位牌を作っても良いか
位牌に「一つでなければならない」という決まりはありません。
例えば、両親の位牌を子どもたちがそれぞれ持ったり、夫の位牌を別々に住む妻と子どもが持ったりすることも可能です。
もちろん、同じ位牌を複数作っても良いですし、それぞれで別のデザインを作成しても問題ありません。
位牌を置く場所に合わせて、サイズやデザインを選びましょう。
白木位牌をそのまま使用できない?
本位牌を作らず、そのまま白木位牌を使えないかと疑問に思う人もいるでしょう。
もちろん、使い続けてはいけないという決まりはありません。
しかし、白木位牌は高さがあることから、仏壇へ置くにはサイズが合わないことも多いです。
故人様が亡くなったことを悲しむ気持ちを切り替えるためにも、四十九日の法要までに本位牌を準備することが望ましいです。
位牌の選び方【種類】

位牌には「白木位牌」と「本位牌」の2種類があり、使う時期が異なるとご紹介しました。
ここからは、それぞれの位牌について詳しく見ていきましょう。
白木位牌
白木位牌は仮位牌とも呼ばれ、亡くなった後すぐに準備します。
四十九日を迎えると本位牌に替えるため、白木位牌を使用するのは、葬儀から四十九日までの期間です。
白木で作られており、戒名などの文字は直接刻んだり、紙に書いたものを貼り付けたりします。
四十九日以降は、お寺に納めてお焚き上げにするのが一般的ですが、お寺や地域で対応はさまざまです。
お寺によっては埋葬したり、お墓に祀ったりすることもあるため、白木位牌の扱い方はお寺や自治体に確認してください。
本位牌
本位牌は四十九日法要において、白木位牌から本位牌に替えられます。
これは、故人様が四十九日で成仏するとされているためです。
黒い塗りの位牌をイメージする人が多いですが、近年はさまざまな種類の位牌があります。
板位牌
個別に作る位牌のことを板位牌といいます。
初めて位牌を作る場合は、板位牌が一般的です。
板位牌の形状は、台座に対して垂直に礼板が立てられています。
個別に作られる位牌のため、1名様用であることが一般的ですが、夫婦で1つの板位牌を作ることも可能です。
繰出位牌
板位牌に対し、繰出位牌は先祖代々の位牌を一つにまとめたものです。
形状は箱型となっており、戒名が記された板を10枚ほど収納できます。
板位牌から繰出位牌へと移す時期は、三十三回忌や五十回忌のタイミングが多く、最後の法要となる「弔い上げ」と呼ばれています。
初めて作る位牌は、故人様一人の板位牌であることが多いですが、地域によっては最初から繰出位牌を作るところもあるため、あらかじめ確認が必要です。
漆位牌
漆位牌とは、木材に漆を黒塗りし、金箔や金粉で加工を行った位牌です。
本漆を使用したもののほか、合成漆を使用したものもあります。
塗りや磨きなど、複数の工程から作られますが、工程が多い、あるいは少ないといった違いがあります。
唐木位牌
唐木位牌とは、高級銘木とされる黒檀や紫檀の唐木を使用した位牌で、温かみのある木目が特徴です。
上品さが感じられながらも、しっかりとした重量感があり、耐久性にも優れています。
ただし、黒檀や紫檀は国際的に保護されており、伐採数が限られていることに加え、成長に時間がかかるため、希少性が高いです。
黒檀が使われた唐木位牌は、遠目だと漆位牌のように見えることがあります。
紫檀とともに高価な素材として重宝され、全国的に木材の需要が高いことから、今後はさらに貴重なものとなるでしょう。
天然木位牌
唐木位牌には、ヒノキやサクラなどの天然木が使われており、優しい風合いが特徴です。
シンプルかつナチュラルな仕上がりは、さまざまなテイストのインテリアにも馴染みやすく、高い人気があります。
近年、木目調の仏壇が増えてきていますが、天然木位牌との相性が良いです。
なお、広い意味では、唐木位牌も天然木位牌に分類されます。
モダン位牌
モダン位牌とは、おしゃれで自由なデザインの位牌の総称のことで、特に決まった定義はありません。
素材も多種多様であり、木製とは限らず、天然石やガラス素材のものもあります。住環境に馴染みやすいことから、近年は需要が増えてきています。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をご用意しており、お客さまのご要望に沿って、オーダーメイドで作成致します。
また、全国対応しており、送料無料で最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌ならば、ぜひお位牌Makerにご依頼してみてはいかがでしょうか。
過去帳
過去帳とは、家ごとに伝わる系譜を指し、故人様の俗名や戒名、没年月日などが記載されたものです。
素材は紙のほかに、布や木が使われることもあります。
仏壇の見台に置いたり、引き出しにしまったりと、普段の置き場所に決まりはありません。
浄土真宗では「亡くなるとすぐに仏になる」とされているため、位牌を作らず、過去帳や法名軸を作ります。
法名軸
法名軸(ほうみょうじく)とは、仏壇の側面に飾る掛軸をいい、主に浄土真宗で使われているものです。
死亡年月日と法名が記載されており、過去帳とともに使われます。
法名とは、浄土真宗で亡くなった人へ授けられる名前を指し、仏門に入るのではなく、仏弟子になることで授けられることが戒名との違いです。
位牌の選び方【デザイン】

ここからは、位牌のデザインを選ぶ場合、留意すべきポイントをご紹介していきます。
デザインを選ぶポイント
位牌のデザインは「伝統的なデザイン」「現代的なデザイン」の2つに分けられます。
仏壇や部屋のインテリアには、どちらのデザインが合うのかを考え、調和する位牌を選びましょう。
伝統的なデザイン
伝統的なデザインの位牌は、金箔や漆が使われており、古来より受け継がれていました。
色は黒や金が多く見られ、格式高く、厳かな雰囲気を持っています。
歴史や古くから伝わる文化が感じられることから、故人様への尊敬や感謝の気持ちを表すのに適したデザインといえるでしょう。
現代的なデザイン
現代的なデザインの位牌は、シンプルな仕上がりが特徴です。
これまでの伝統的なデザインの位牌には使われなかった素材、色、形が使われており、おしゃれでモダンな印象のものが多いです。
現代の住空間に合わせやすいデザインですが、文字の入れ方は従来どおりの方法を継承しています。
リビングに仏壇が配置されている家も多く、洋室には現代的なデザインが馴染みやすいでしょう。
デザイナーの位牌
近年では、デザイナーが手掛けた位牌の需要が高まってきています。
一見すると仏具とは思えないようなデザインもあるため、インテリアにこだわっている家でも、違和感なく馴染むのがポイントです。
モダンなデザインの仏壇に合うことはもちろん、仏壇を置かずに位牌だけを祀る場合にも重宝されています。
文字の色には意味がある
位牌に入れる文字は、金色が主流で、生前位牌では戒名に朱色が使われます。
現在では、金と朱色のほかに、位牌のデザインに合わせて別の色を使うこともあるのです。
日本では位牌に限らず、冠婚葬祭において色に位があり、格式の高さを色で表現できます。
もっとも位が高い色とされているのが「金」です。
続いて「銀、紫、赤、藍、緑、黄、黒」の順に格式が高い色とされています。
ただし、白い位牌の場合、金よりも紫や藍などの深い色を使うほうが映えることがあり、金にこだわる必要はないでしょう。
また、木目の位牌の場合には、金よりも黒が映えます。
ポイントとしては、全体的なバランスを見ながら、色を選ぶと良いでしょう。
色やデザインにこだわりがない場合や、無難に作りたい場合は、金色を選ぶと安心です。
位牌選びでよくある失敗

位牌を初めて作る人も多いのではないでしょうか。
また、位牌とはどういうものなのかを知らない方も少なくないため、いざ作ろうとしても、どのように選べば良いのか分からないかもしれません。
そのような状況で位牌を選ぶと、失敗して後悔する可能性も考えられます。
ここでは、位牌選びで起こりやすい失敗と、失敗しないための対策をご紹介しましょう。
文字がイメージと違う
位牌の失敗で多いものは、文字に関するものです。
文字の大きさがイメージと違う、文字がイメージしていたものよりも目立ってしまう、あるいは目立たないといった失敗があります。
位牌の文字はバランスが大切です。
文字数が多く、位牌のサイズとバランスが取れていない場合には、文字が詰まってしまいます。
反対に、文字と文字の間が空きすぎても、うまく調和できません。
位牌の文字には、機械彫り・手彫り・機械書き・手書きの4種類があり、扱う手法は店舗によって異なります。
手彫りや手書きの場合、温かみや味のある文字に仕上げることが可能です。ただし、イメージと違う仕上がりとなるリスクは、機械彫りや機械書きよりも大きいです。
そのため、どのような文字に仕上がるのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
位牌の品質が思うようなものではなかった
位牌の失敗として、品質に関する事例も多く見られます。
特に安価な場合には、塗りにムラがあるなどの出来も見られるため、注意が必要です。
また、現代的なデザインの位牌においては、イメージしていたものよりも簡素に見えるといった失敗例があります。
これらのことから、位牌選びに失敗しないためには、価格が安過ぎるものを避けることが大切です。
位牌を選ぶときの注意点

位牌を選ぶに当たり、気をつけなければならないポイントがあります。
それでは、どのような点に気をつければよいのか、選び方の注意点を見ていきましょう。
価格だけで選んではいけない
位牌を購入するときは、欲しいと思って購入するというよりも、必要に迫られて購入する場合がほとんどなのではないでしょうか。
そのため、つい安価なものを選んでしまう傾向にあります。
しかし、安価なものや高価なものには、その価格である理由がきちんとあるため、安過ぎるものを選ぶと失敗する可能性は高いです。
安価だからと価格だけで選ぶ場合は、なぜ安いのか理由を理解した上で、納得して購入すれば失敗を防げます。
位牌原稿を確認できる店舗で購入する
位牌選びを失敗しないためには、位牌原稿で文字を確認できる店舗を選ぶことが大切です。こだわりがある場合ならば、特に位牌原稿の有無に注目してください。
また、インターネットで購入する場合には、入力した文字が位牌にどのように入るのか、公式サイトで事前に確認できる店舗を選びましょう。
レイアウトのみならず、誤字や脱字がないかどうかも、忘れないようにチェックしてください。
彫りの品質と仕上がりを確認する
先祖を祀る位牌は品質も重要です。
そのため、彫りの品質や仕上がりをよく確認しましょう。
木製の位牌であれば、木目に沿って彫られているかどうか、塗りの位牌の場合には、彫られた文字に接している部分の塗装状態を確認してください。
なお、見本をチェックする場合は、拡大して細部まで確認することが大切です。
宗派や地域のルールを確認する
位牌のルールは、宗派や地域により、一般的なルールと異なる場合があります。
そのため、オーダーする前には、お寺へ確認してください。
また、地域によって使われる素材が決まっている場合もありますが、最近では自由度が高くなっていることから、以前ほど気にしなくても良くなっている場合も考えられます。
宗派による違いでは、浄土宗や真言宗などの宗派により、位牌のデザインが異なります。
デザインの違いは、文字の色やレイアウト、金箔を使用するかどうかなど、さまざまな影響があるため注意が必要です。
もしもデザインを決めた後、宗派によるデザイン変更を余儀なくされた場合は、デザインのみならず決めた内容すべてを変えなければならない可能性があります。
まとめ
本記事では、位牌の選び方についてご紹介し、選び方のポイントや、失敗しないための注意点などを解説しました。
位牌の選び方は、種類が豊富となっていることから、以前と比べて大変に感じてしまうかもしれません。
しかし、細部までこだわりたい人や、おしゃれなデザインを選びたい人にとっては、満足できるものを選びやすいということです。
これから位牌を作る人は、ぜひ本記事の内容を参考にして、空間に調和するデザインや、納得できる品質の位牌を選んでください。
また、宗派や地域でルールがある場合には、そのルールに合わせて選びましょう。